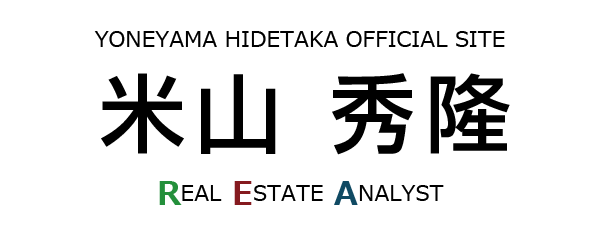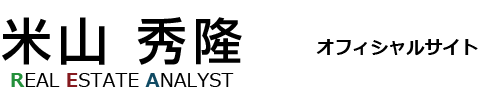慢性的に供給過剰な賃貸物件
よく知られているように、不動産は現金に比べて大幅に評価を減らせるため、相続対策として、しばしば賃貸物件が建設・取得される。
まず、土地の相続税評価額は路線価をもとに算出されるが、路線価は土地取引の目安となる地価公示の8割程度である。貸家を建設すると、「貸家建付地」として評価されることになり、更地のままにしておくよりは、2~3割ほど低くなる。さらに、不動産の貸付として使っている土地は、小規模宅地の特例の制度を使うことにより、200㎡までは5割引となる。このように、貸家建設によって、土地の相続税評価額を圧縮できる。
建物の相続税評価額については、固定資産税評価額が使われ、これが建築費の7割程度までとなっている。さらに、賃貸にすると固定資産税評価額の7割程度になるため、結果として実勢価格の半分程度の評価となる。つまり、現金のまま保有している場合に比べ、相続税評価額を半分程度に圧縮できる計算になる。
さらに、貸家の建設資金を金融機関から借り入れた場合、借入金を相続財産から差し引くことができる。
こうした税制上のメリットにより、日本の賃貸住宅市場では、実需を満たす以上に物件供給がなされている。総務省「住宅・土地統計調査」によれば、賃貸物件の空室率は18.5%(2018年)に達するが、これは例えば10%ほどのアメリカに比べれば極めて高い。次々と供給される新築物件に需要が向かえば、既存物件の空室率は上昇する一方になる。
これを空き家問題の観点から捉えると、オーナーに募集の意向があり、物件が管理されていれば空室が増えても問題がないが、そうでなければ、戸建ての空き家問題と同様、老朽化の進展とともに、管理不全の物件がいずれ大量に朽ち果てるという問題が生じかねない。現に大分県別府市では、朽ち果てた賃貸物件を代執行するのに500万円ほどかかり、しかも所有者不明で回収できなかった例がある。
資産圧縮幅を抑える動き
2015年1月からの相続課税強化に伴う貸家建設ブームは一段落したとはいえ、慢性的な供給過剰をもたらす日本の賃貸住宅市場の構造をこのままにしておいて良いのかという問題意識は、着実に高まっている。
過去にも過度な歪みが生じた結果、封じられた相続対策はいくつもある。例えば、生命保険や年金を活用した相続税対策(終身保険と相続税法26条を活用したプランなど)は、税制改正により今はできなくなっている。こうした結果として、貸家建設・取得による資産圧縮がもてはやされた面もあるが、現在においては、貸家建設・取得が相続対策として過度に有利になる仕組みを改める必要性が増している。それは、住宅市場の歪みをもたらす問題につながるが、国税当局にとっての深刻な問題は、過度な節税対策の横行が、税負担の公平性を脅かすということである。
そこで近年は、これを是正しようという動きが出ていた。まず、賃貸物件建設に関しては、小規模宅地の特例については一昨年春、相続開始前3年以内に新たに賃貸業を始めた場合、特例が使えなくなる法改正があった。相続直前のあからさまな相続対策に歯止めをかけようとするものである。
また、賃貸物件取得に関しては、タワーマンション投資のメリットが減殺された。タワーマンションについては、一頃、高層階の部屋を購入して相続税を節税する方法がもてはやされた。タワーマンションの相続税評価は、高層階でも低層階でも同じになる点に着目し、時価が高い高層階を購入することによって相続税評価額をより圧縮するというものだった。これについては、国税庁が評価の見直しを行い、やはり一昨年春から、相続税評価額が、高層階がやや割高に低層階がやや割安にされることになった。
しかしこれはタワーマンション高層階が他の賃貸物件取得に比べ有利になる点を手直ししたものに過ぎず、賃貸物件一般を取得した場合の資産圧縮幅にメスを入れるものではなかった。
相続税評価をめぐる東京地裁判決
これに対し、今後、相続対策としての賃貸物件取得に影響を与えるものとして注目されているのが、路線価に基づく相続財産の評価は不適切とした昨年8月の東京地裁判決である。
この裁判は、2012年6月に94歳で亡くなった男性が購入していたマンション2棟(杉並区、川崎市)の評価額をめぐり、相続人(3人)と国税側が争ったものである。2棟の購入額は13億8700万円で、購入から2年半~3年半で男性が死亡し、相続が発生した。相続人は、路線価に基づき2棟を3億3千万円と評価し、銀行からの借り入れ額を差し引き、相続税額ゼロで申告した。しかし、国税側の鑑定では2棟の評価額は12億7300万円と路線価とは大きくかけ離れていたため、路線価による評価は適当ではないとし、3億円の追徴課税処分を行った。これに対し、相続人は取り消しを求めていた。
国税庁は、財産評価基本通達で土地、建物などの評価方法を定めており、相続人もこれに従って申告した。しかし、同じ通達の6項では、特別の事情がある場合には、路線価以外の合理的な方法で評価することが認められている。今回のケースでは、通達の評価方法をそのまま適用することは、税負担の公平性を著しく害する特別な事情に当たるとする、国税側の主張が認められた。
つまりこのケースでは、マンション取得が相続発生直前で、しかも実勢価格と路線価の間に著しい乖離が発生したことが、節税対策の行き過ぎと判断されたことになる。しかも借り入れ先の銀行の稟議書には、相続対策の不動産購入を計画などの記載もあった。
賃貸物件供給に歯止めがかかるか
今回の判決により、今後は賃貸物件取得で相続対策を行おうとする場合、国税の「伝家の宝刀」ともいえる6項により、行き過ぎと指摘されかねないというプレッシャーを受けることになる。6項の適用条件は明示されてはいないが、国税庁内の資料では、基本通達の評価方法を形式的に適用する合理性がなく他に合理的な評価方法があること、また、2つの評価額に著しい乖離があり、その乖離が納税者の行為介在によって発生したものであることの2点とされている。要するに路線価と時価に大きな差があり、しかも物件取得後短期間で相続が発生するなど、直前の相続対策が大きな効果を生むあからさまなものは容認できないということであろう。
筆者はかねてから、貸家建設・取得が相続対策として過度に有利になる仕組みを改める必要性を主張していたが、政治的には難しいと考えていた。政策的に評価額の圧縮幅を縮小しようとしても、政治家にとっては支持者の獲得という意味ではメリットはあまりなく、むしろ富裕層の支持を失う可能性があると考えられるからである。今回、国税が税負担の公平性という、社会正義の側面から切り込み、また、裁判所がこれを支持したのは画期的といえる。相続人は判決を不服として控訴したが、今回の判決内容は上級審でも支持されてしかるべきである。判決の効果が浸透していけば、節税対策の物件建設・供給にもじわじわと影響が及んでいく可能性がある。