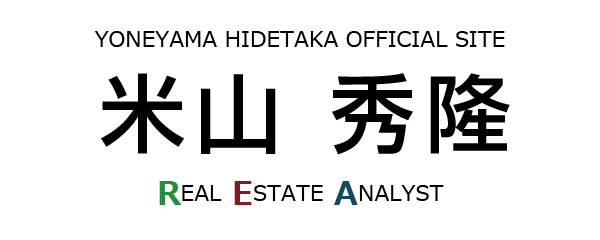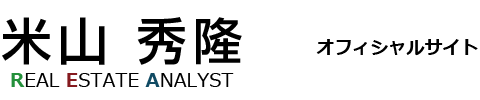テレワークで生産性が向上するケース
コロナ禍後に活用が進んだテレワークであるが、現在も一定の実施率を保っている。東京都区部で、ほぼ100%の実施から不定期の実施まで、何らかの形でテレワークを行っている就業者は今年6月時点で50.6%に達する(内閣府調べ)。週何回かはテレワーク可能など、ハイブリッド勤務を維持している企業が多いと思われる。企業としては、テレワークの生産性や労務管理上の問題に目をつぶりつつ、人材獲得競争上の必要性からも、テレワークを維持せざるを得なくなっている。
米国でテレワークの生産性を分析した興味深い研究がある[1]。米国特許商標庁の特許審査官(高学歴の専門職員)に導入された全面テレワークの効果を分析したところ、4.4%の生産性向上がみられた。手戻り(出願人からの申立を受けた後の審査結果の書き直し)の大幅増加や、特許品質(審査官が引用する回数で判別)の低下も見られなかった。
特許審査官のように業務の独立性が高く、従業員が仕事を熟知している場合は、生産性が上がるという結論で、これは仕事がほぼ1人で完結する場合は、テレワークで生産性が上がりそうだという直観とも一致する。
この研究結果は、その仕事が置かれた状況がテレワークに適している場合、つまり、業務の独立性が高く、従業員が仕事を熟知している場合、テレワークの導入は企業にとっても従業員にとってもメリットがあるということを意味する。
従業員にとってのメリットとしては、働き方の自由度が高まるというメリットのほか、実質賃金を高める効果があった。これは特許審査官が平均して物価の安い場所へ引っ越したことによる。また、勤続年数が長く定年に近い審査官は、定年者にやさしいフロリダの海岸沿いのエリアに移住する傾向があり、こうした居住地の移動は、高齢者が長く働くための一助になる可能性が浮かび上がった。
一方、雇用主にとっては、テレワーク導入に様々な困難が伴うにしても、生産性が全体として上がるのならばメリットがある。
実際のところ、テレワークの実施可能性や生産性は、業種や職種、タスクによって異なるが、実施可能な場合、週何回か、1人で集中して作業を行うために認めるという方法は、企業としての1つの妥協点になっているともいえる。
テレワークで賃金上昇は抑制される?
テレワーク運用上の課題に対しては、これまでも様々な解決策が提案[2]、模索されてきた。働く時間帯が異なると、ブレインストーミングや同期型コミュニケーションに困難が生じることに対しては、例えばスラック・チャネルなど非同期型コミュニーションを活用することがあげられる。知識共有が難しいという点については、会議記録などを保存して、都合の良い時にアクセスできるようにすることがあげられる。仲間意識が希薄化して孤立しやすいという点については、メンバーが不定期に集まるランダムな交流の場をオンラインで提供することなどがあげられる。
テレワークする従業員のスキルを評価して、適切な賃金を支払うのが難しいという問題に対しては、労働時間を管理するのではなく、成果物の質や顧客からのフィードバックを評価に加えることなどが提案されてきた。
評価の問題は特に難しいと考えられるが、これに対しては、テレワークする従業員と出社して勤務する従業員によって、あるいは従業員の居住地によって、賃金に差をつけるというのも、考え方としてあり得る。働く時間や場所が柔軟な場合、賃金が多少低くても労働者は受け入れる可能性が高く、逆に柔軟性を欠く職務の場合は、賃金割り増しが必要になるという考え方である。一方、生産性の観点から言うと、テレワークの生産性が平均的には出社勤務に劣るとすれば、テレワークに対しては低い賃金を支払うのが正当ということになる。
特許審査官のケースでは、物価の安い地域に住めるようになった結果、実質賃金が高まる効果があった。この点を雇用主の立場から見て、従業員の実質賃金が一定に保たれれば十分と考えれば、テレワークを広範に認めることで名目賃金を引き下げる余地が生まれることになる。こうした考え方に立つと、テレワークのより一層の普及は、将来的には賃金上昇を抑制する可能性もある。
参考文献
チョードゥリー,プリトラージ、バーバラ Z. ラーソン、シーラス・フォローギ(2019)「従業員に『働く場所の自由化』を認めるべきか」『ハーバード・ビジネス・レビュー』9月
チョードゥリー,プリトラージ(2021)「従業員が場所を問わずに働く『ワーク・フロム・エニウェア』を実現できるか」『ハーバード・ビジネス・レビュー』4月
[1] チョードゥリーほか(2019)による。
[2] チョードゥリー(2021)による。